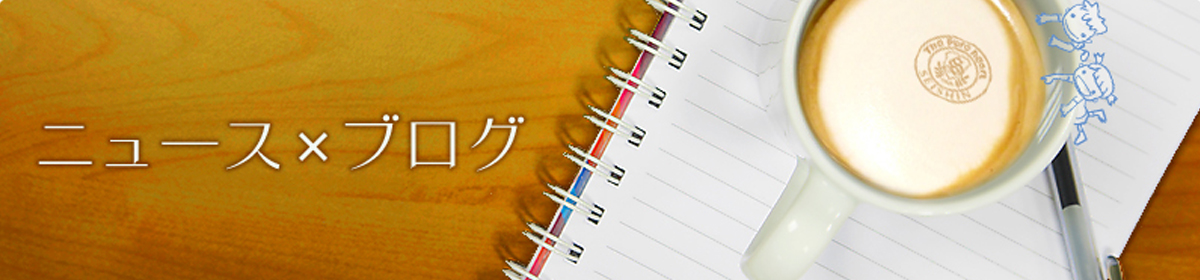そんなふれこみが、あったのでいってみると・・・
こんな感じになっていました!かわいい!!
でも、この姿の前には、昨日と今日にかけて、
何人かが入ったり、出たり、また、子ども同士の
試行錯誤やぶつかり合いもありました。
そうしたプロセスも含めて、子どもたちの遊び(育ち)に
なっていくのだなぁと思います。
投稿者: staff
【ようちえん開放日2014】第1回目は4月25日(金)です。
2014年度の「ようちえん開放日」のご案内です。
第1回目が4月25日(金)です。
1歳児以上であれば、どなたでも参加できます。
どうぞお出かけください!
【2014年度ようちえん開放日(5月は毎週金曜日)】
■日時:1回目:4月25日(金)9:30~11:30
■場所:清心幼稚園
■対象:満1歳以上の親子
*園内で遊べます。見学もできます(予約不要)。
*駐車場には限りがあります。
*上履きは必要ありません。
***********************************
こちらは、今年度、プレクラスに通っていた2歳児の姿です。
園庭の砂と水を混ぜて、おだんごにしていました。
そのかわいい手におさまらないくらいの、おだんごに
なってきているのがわかりますね!
慣れてくると、このように、自分の好きなことを見つけて、
じっくりと対象と関わりながら遊びます(遊びこみます)。
ちなみに幼児は、遊びこむ中で、小学校以降に必要な
「主体的に活動する力」が育つと、言われています!
そのための環境には、時間やモノ、空間、人を十分に
用意することが大切だそうです。 「ようちえん開放日」を
「お子さまの遊び場」にすると、きっといいと思います。
【年少】せんろ、ない!
先週、年長さんや年中さんと遊んだ電車ごっこ。
今日も続きで遊ぼうとした年少児の数人が・・・
幼稚園の中をぐるっと回って、
「せんろ、な~い!」
そうなのです。
年長児が 卒業式を前に 線路を外して いきました。
何人もの保育者に、「せんろ、どこ? しってる?」と
聞いて回る 年少児たち。そして・・・
保育者:「せんろ、つくっちゃえばいいんじゃない?」
年少A&B:「・・・・。」
保育者:「ざいりょうとかさがして、ね」
年少A:「そっか、つくろっか?」
年少B:「つくろ、つくろ!」
そして、線路や駅をつくり始めて、遊んでいたのですが・・・。
しばらくすると、そこに子どもの姿は ありませんでした。
(この時期、あちこち遊びが移っていくのも よくあります)
でも、フラフープを電車に見立てて、走る様子に、
年長児たちが遺した 遊びの文化が 垣間見えました。
【研修報告】「ワークショップと学びとその後」
昨日、表題の研究報告会が、青山学院大学でありました。
(主催:アンラーニングワークショップ研究会)
2012年発刊の「ワークショップと学び(全3巻)」(東京大学出版会)を
執筆された先生方を中心に、講演や実践報告が行われました。
その中で、佐伯胖先生が、学校でも、社会でも、
「なんでも『こうすれば、こうなる』をやめて、
『子どもの中に驚く』ことが大切」と、話されていました。
幼児教育はもちろん、学校や、社会がそういう視点で
子どもや児童を見るようになったら、きっと、
私たちの学び方や、考え方、教え方も変わるでしょう。
ちなみに、最近の佐伯先生は、学生たちに、
“教えないことを 教えている” そうです。
なるほど~。
119回目の卒業生をおくることができました。
本日、幼稚園生活を修了し、年長さんたちが 旅立ちました。
いろいろなこと、ぜんぶ経験になっているよ。
みんなには、たくさん驚かされました!
だから、毎日の生活が楽しくなったし、
あなたたち同士で、育ち合っていたと思います。
私たちにも、たくさんの学びがありました。
どうも、ありがとう! また遊びに来てね。
【年少⇒年長】「おーい!」
(年少さんの帰り際、2階の年長さんを 大声で呼んでいたよ)
「あそんでくれて ありがとうー!」
年長さん、その声に気付いて、ベランダへ!
「こちらこそー!」「げんきでねー!」「ばいばーい」
お互いの声が 飛び交います。
明日は卒業式。年少さんと年長さんが 会えるのは 今日までです。
胸がキュッと 熱くなりました。
子どもたちに、ざくろさん流のメッセージ♪
この1年間、子どもたちと過ごしてきた、山賀ざくろさん(ダンサー)。
「アーツ前橋プレイベント」の出演に 子どもたちを 誘ってくれたり、
園で一緒に 遊んできたりしました(今日は流し風!?)。
そんなざくろさん。年長さんと過ごすのも あとわずか・・・
そして、卒園生に贈る歌 「春風にのって」を 作ったそうです。
どんなふうに 聞こえた(届いた)のかな。
保育後の光景・・・
この痕跡に思わず、微笑む。
冷めやらぬ空気感。きっと明日も続くだろう。
まだ、ほかほか 湯気が立っている。
「みそしる」と「電車ごっこ」で、おかえし。
朝から準備が進み・・・
(みそしるづくり)
畑から 大根をとってきて 下ごしらえ。
鍋ごとに ダシが違います。
(電車ごっこ)
途中から 単線が複線に。
表記も楽しい!(杭の深さも違うらしい!!)
そして・・・たくさんの 電車が走った!
みそしるも 振る舞われた!
「自分たちの過ごす時間を、自分たちがつくる」
今年の 5歳児ならではの、アイディアと愛情に あふれた1日が、
こうして また一つ生まれました!
****************************************
私たち保育者が、イイと思って計画し、子どもたちに
やらせることは簡単だ。しかし、それでは、保育者の「指示に従う子ども」、
「考えない子ども」を育ててしまう。
子どもにとって、はるかに難しく、意味があることは、
自分たちの生活を 自らつくっていくことだ。
その主体性が、将来の育ちに続く力になる。
だから、時間、 空間、モノ、ヒトが、十分に保障され、
子ども同士の関わり合いが たくさんある 保育環境で
過ごすことを ぜひ、おすすめしたい。
݊
【年長】「びっくりパーティー」のおかえしに。
先週の金曜日、いくつかのアイディアがでました。
そのうちの一つがコレ。「みそしるのプレゼント」。
振り返ってみますと、彼らはそういう体験をしてきました。
「みそしる」の材料さがしへ。(2013/12/3付)
「みそしる」をつくる。たべる(2013/12/6付)
自分たちが前に楽しんだ「みそしる」を、振る舞う・・・
「みそしるをつくる」という行為が、きっと、
子どもたちの経験になっていたのでしょうね。
ちょっと、できすぎな話にも聞こえますが、
「〇〇をしてあげたい!」という気持ちに
保育者も乗っかって、準備することになりました。
そして、もうひとつ。「電車ごっこをしたい!」と・・・
突然、「てつどうはくぶつかん」づくりが始まりました。
それから、「電車に乗せてあげたい!」と、駅ができ、
電車が走るための線路づくり・・・と。
こちらも 明日、出来上がったら、始まるようです。
お返しをするのも、いろいろな方法がありますね。
子どもたちの表現が多様に出せる場が保障され、
お返しをするための作業ではなく、自分たち自身もそこで
楽しんだり、遊んだり、本番を想像したりする・・・
そういう子どもの姿は、それまで無関心だった子に飛び火して、
あっという間に、遊びのかかわりも広がっていきました。
***************************************
実は・・・
こんな時期から続く遊びの題材です(2012/5/30付)。
題材は同じですが、この時とは、遊びの目的も姿も違います。
私たちは、こうした子どもの姿を文字や写真等で記録しながら、
子どもの育ちを見ようと心掛けています。
また、最近は、各ご家庭に、お子さまの過ごしている姿を、
写真やエピソードを通してお伝えするようにしています。