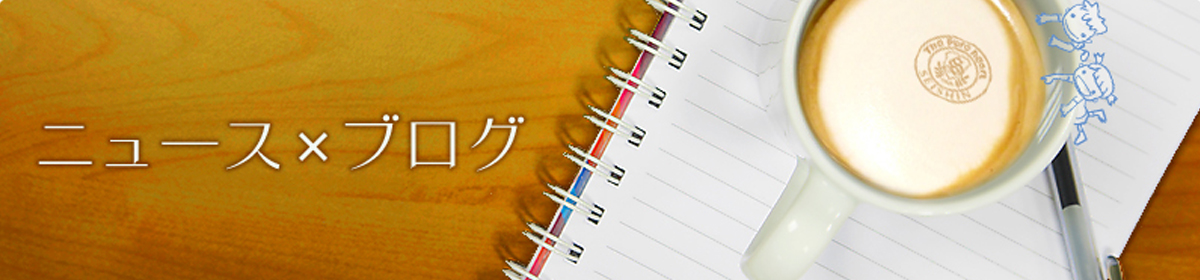イワシのアタマは、節分用の「ヒイラギイワシ」になりました。
では、カラダはというと・・・
木切れを燃やして、
木炭に火を点け、
七輪で焼いて、
ひとつまみずつ 分け合って いただきました!
【ウインターピュアわ】ゆきあそび@志賀高原
2月2‐3日で、ゆきあそびに 行きました。
これは、毎年、希望者の親子で出かけています。
ゲームをしたり、スキーをしたりして、雪といっぱい戯れました。
天気もそこまで悪くならず、気持ちよかったです。
とくに3日は、アルプスの山々が キレイに見えました!
今年は志賀高原での開催でしたが、さて、来年は・・・
先生のあたまの上に、つみきを7つのせてみよう。
本日のブログ担当の中島佑太です。
12月から小学生対象のワークショップクラブが始まりました!
クラブの名前はまだありません。何か良い名前があったら教えてね。
記念すべき第一回目のワークショップは、〈空の積み木〉を使ったワークショップです!
空の積み木は、中島佑太が2012年10月にBSフジで放送された
「つながるアート☆エコトラの旅」(日比野克彦監修)の番組のために制作した
空模様の積み木です。東京深川、福島、仙台、山形県新庄の小学生と一緒に
廃材から作ったエコな積み木!
詳しくは→http://houseof.exblog.jp/16801973/
今回はその空の積み木を使って、中島が出題した5つのミッションに答えながら、
普段とは少し違う積み木遊びをしてみよう!というもの。
そのミッションとは!?
ミッション01
自分の背より高くつみきをつみあげて、下から見上げてみよう。
ミッション02
先生のあたまの上に、つみきを7つのせてみよう。
ミッション03
ともだちがもっているつみきの上で、つみきあそびをしてみよう。
ミッション04
あおい空のほかには、どんな空があるかな?
空のつみきをつかって色んな空をひょうげんしてみよう。
ミッション05
5つめのミッションを考えてみよう。そのミッションを友だちにやってもらおう。

清心幼稚園の卒園生以外も参加できるワークショップなので、
初めてのお友達も来てくれました。初めて会う子ともすぐに打ち解けながら、
床の上で積み上げるだけではなく、友達の腕の中や、背中の上や顔の上に
積み木を積み上げて、いつもとは違う空の形を見上げます。

5つめのミッションは、すぐに考えられるグループと、
なかなか思いつかないグループがありましたが、
最後はホールにあったコーン(パイロン)をつかって、
空のアイスが生まれました!

与えられた素材だけではなく、回りにある環境を活かしながら新しいアイデアに
つなげていく!これぞワークショップの醍醐味と言えますね。
赤いコーンをアイスのコーンに見立てて、みんなが大好きなアイスにしてしまうのもステキ。
あと、この空のアイスは誰かに支えていてもらわないと、
倒れちゃって作れない!ワークショップでは、
1人ではできない形やおもしろいことがたくさん生まれます。
作品は形に残して持ち帰れるものだけではありません。
ものより思い出、なんていうコピーも昔ありましたが、
“出来事”をつくり、”記憶”に残し、”新しい考え方や視点”を持ち帰る、
そんな形の作品もあるんです。


次回のワークショップクラブは2013年2月9日[土]に『ひみつのさんぽかいぎ』を予定しています。
詳しくは清心幼稚園へ!
「アートは被災地を支援できるのか?」シンポジウム開催。
「遠足プロジェクト@まえばし」~おもいをはこぶランドセル~ が開催されます。

被災地への支援物資のひとつ「ランドセル」。
本プロジェクトは、使用されずに廃棄処分となった中古のランドセルを
譲り受けたアーティストが、アート作品として生まれ変わらせた巡回展です。
【作品展示&ワークショップ】
■期間:2月17日(日)~23日(土)
■会場:前橋児童文化センター
■ワークショップ①ぐんまダルマプロジェクト 2月17日(日)10:00~16:00 児童文化センター
ワークショップ②「遠足ワークショップ」 2月18日(日)13:00 前橋駅北口集合
ワークショップ③作品鑑賞ワークショップ 2月23日(土)13:00~ 14:00~ 児童文化センター
*************************************************************************
清心幼稚園は、本プロジェクトの「シンポジウム会場」です。
【シンポジウム】
■テーマ:「アートは被災地を支援できるのか?アート・コミュニティ・美術館」
■日時:2月24日(日)12:30~15:30
■場所:清心幼稚園ホール他
■司会:茂木一司(群馬大学教授)
パネラー:梶原千恵(石巻市門脇中学校)
武谷大介(アーティスト)
住友文彦(アーツ前橋)
長田謙一(首都大学東京教授)
コメンテーター:中島佑太(アーティスト)
■子ども向けワークショップ同時開催(要予約・内容未定)
ワークショップの予約先:清心幼稚園(027-231-2715)
*************************************************************************
■主催:遠足プロジェクト@群馬大学実行委員会
■協力:前橋市/前橋児童文化センター/学校法人清心学園清心幼稚園
■後援:上毛新聞社/特定非営利法人WSD推進機構
■問い合わせ先:藤原秀博(080-3240-8710/hidefuji0409@gmail.com)
*************************************************************************
すべて無料です。
どうぞお気軽にご参加ください!
気持ちのいい豆まき。
園庭に とつぜん現れた!
年中さんや年少さんが準備していた「ひいらぎイワシ」や福豆の買出しを
遠目に見たり聞いたりしていた 年長さんの何人かが変身。
「おにはー そとー!」 「ふくはー うちー!」
オニも負けていません。 豆を拾って、すぐさま投げ返します。
あっ、2階のベランダからも豆が飛んできた!
【年中】豆まきの準備をする②(ひいらぎイワシを作る)
園庭でイワシをさばくことになった。
なぜなら、イワシのアタマが必要なのだ。
イワシをよくみてみる。 そして切ってみる。
そのアタマに、普段遊びで使っている木切れを 刺してみる。
ヒイラギの葉が見当たらず、 代用品を見つけてきたのだ。
できあがったものをこんな風に並べていた。
これから、どうなるのかなァ、と思ってみていると、
保育室の前に砂山を作って、各部屋ごとに立てていた。
こうすれば、きっと鬼も部屋の中には入ってこないだろう。
なかなかの思いつきだと思った。
【年少&年中】豆まきの準備をする①(豆とイワシの調達)
年中の子どもたちから、鬼を追い払うには 「豆とイワシが必要」との話がでた。
「じゃあ、買いに行こう!」と、年中さんと年少さんが協力して出かけることに。
そこで、豆チームは、「フレッセイで売ってる」と、フレッセイ(スーパー)へ。
一方、イワシチームは、魚屋(「魚健」さん)へ。
途中、道が分からなくなって迷っていると、秋葉写真館の秋葉さんが
地図を見ながら教えてくれた。
「魚健」さんに着くと、イワシを買いに来たはずだけど、
子どもたちは いろいろな魚たちに興味津々。
子どもたち:「これなに~?」(アサリを見つけて)
すると、おかみさんがいろいろと見せてくれた。
子どもA:「あっ、いま、水みたいの でた!」
おかみさん:「生きているんだよ」
子どもA:「ちょっとさわりたい」
子どもB:「ぼくもー!」
子どもC:「これあいてる、なんでー?」
おかみさん:「そうね、これもあいているよ」
すると しばらくして・・・・
子どもD:「ねえー、はやくサバを買って もどろうよ」
子どもたち:「えっ、サバ??」
子どもD:「そうだよ、サバだよ」
子どもA:「ちがうよ、イワシだよ」
しばらく「サバ」か「イワシ」かの相談。
話し合いの結果、「イワシ」を5匹買って帰ることに。
帰り際、「何か聞いておきたいことある?」と保育者。
子どもE:「どうやって、ぜんぶの魚を止めてるんですか?」
おかみさん:「そうだねー」と、魚の〆方を教えてくれた。
おかみさん:「難しかったかな? 分かった?」
子どもE:「うん!」
********************************************************
確かにちょっと難しい話しだなァって、思いながら聞いていた。
でも、「魚の〆方」が分かったかどうかが 大事ではないのだろう。
子どもが、自分の経験や 知っている言葉を総動員し、
「魚と対話」するからこそ、「ぜんぶ動いていない」
「どうして止まってるのかな」 「なんかおかしいな」って気がつき、
〆ることで「止まる」ってことが分かったんだと思う。
こうして実感を得ながら 納得していくことが、
より意味のある「学び」になっていくんだろうな。
「もちつき⑥」食材を準備する(あんこをつくる)
ホールではあんこづくりが進行しています。
明日の本番を控えて、もち米をすすいぐ準備も進みます。
「もちつき⑤」食材を用意する(しょう油)
こちらは「榎田醸造」さんのお店の中。
ここまで来るのに、地図を手掛かりに道を探して、
ようやくたどり着くことができました。
店内には、お味噌や漬物などいろいろなものがありました。
お店の方に、しょう油があるのか聞いて・・・
3種類のしょう油が見つかりました!
そして、いつまで使えるのか、量はどのくらい必要なのか、
調べてどれを選ぶか決めようとしました。
しかし、なかなかまとまりません。
すると、ある女児がお店の方に、どれが「おもち」に合う
しょう油か、聞きに行きました。
店員さんは、「真ん中のは少しお出汁が入っていて、ぴったりよ」
と、教えてくれました。
「なるほどー、コレかァ」と、子どもたち。
ところが、どうしても もう1本のしょう油が気になる様子。
「今日ここに来ていない子たちには分からないから、
どっちも見せてあげたい!」
「両方味見をしないと分からない!」
たしかにそれもそうかもしれません。
実際の物を見てもらう、自分の舌で確かめてみる、
体感することが、1番分かりやすいかもしれませんね。
子どもはそういうこともよく知っています。
「もちつき④」食材を準備する(きなこをつくる)
きなこ作りが人気急上昇。まずは買ってきた大豆を炒るところから。
年長さんの保育室に、年少さんも、年中さんも加わって・・・
その後、炒った大豆をすりつぶすのですが・・・ 大豆がとにかく堅い!
すりこぎとすり鉢、すりゴマ器、ビニール袋と金づちと材木、など
どんな方法がいいのか、いろいろ試してみます。
そして、最初は封筒の外側にガムテープを張って、金づちでたたくと良さそう!と発見。
最後に、きな粉と大豆をえり分けて・・・
粒が残っていたらそれを取り出し、再度すっています。
えり分けの基準があるのかな、と思って子どもたちを見ていると、
粉ふるい器の網の目の大きさにその根拠がありそうです。
根気のいる作業を経て、ようやく完成!
「ほっかいどうのくろだいず」「ほっかいどうのだいず」「ぐんまのだいず」
3種類のきな粉ができあがりました。
どんな味がするのかな??