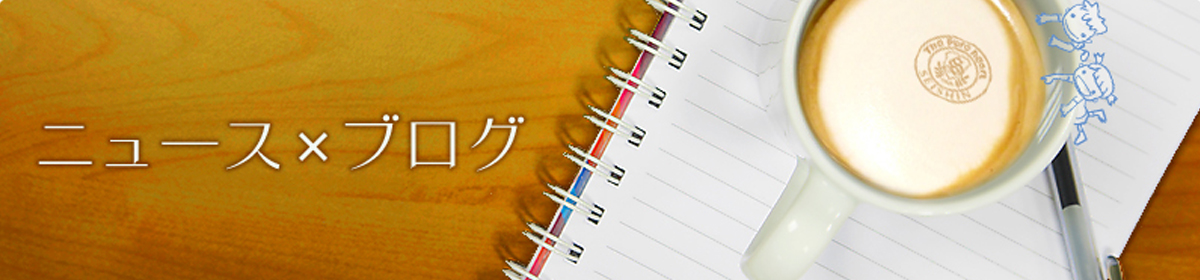清心幼稚園では、通常保育の後、子どもたちが、
ザスパクサツ群馬のコーチと、毎週遊んでいます。
昨日は、ザスパと関係するチーム同士の
キッズサッカー大会も行われました。
そして、本日はトップチームの試合。
スタジアムが改修されて、音響も映像も格段に
よくなりました。でも、まずはいい試合を見せてほしい!
ぜひ、みなさんも足を運んでみてください。
投稿者: staff
中島佑太(アーティスト)の現場で@松戸
ナカジの週末はPARADAISE AIR@松戸の報告会(ナカジの企画)。
パヴェルさん(ポーランド出身。ロンドン在住)を招いて、
滞在(1か月半)しながら制作した作品展示&トークなどが予定されている。
パヴェルさんは、松戸のお年寄りや子どもたちとワークショップや
インタビューを通じて、出てきたものを映像の作品にしていた。
それが、松戸駅から徒歩数分のココ。
土曜の夕方、地元のおじちゃんが「友だち連れてきた」と、
立ち寄っていた。そのくらい気軽なところのようだ。
トレンチ風コートを召したその3人のおじちゃんたちが
この空間で話している風景が、なんかよかった。
**********************************
パヴェルさんは、幼稚園にも遊びに来てくれました。
時間の都合で、在園の子たちとは遊べなかったけれど、
小学生(卒園児たち)と、少し過ごすことができました。
最近は、「アトリエスタ」という、アート専門のスタッフが
常勤している幼稚園や保育園もありますね。
(でも、ナカジが根を生やしたら、きっと枯れちゃう!)
ここ数年の清心幼稚園は、いろいろなアウトリーチのあり方を
考える(問う)場になっているんだなと思います。
「〇〇パーティー」で、年長さんに“ありがとう”を伝えたい。
数日間の準備を経て、「〇〇パーティー」こと、
「びっくりパーティー」が始まった!
パーティーのチケットが配られると、オープン前に行列が。
びっくりさせる人たちも待機して、準備はOK!
「びっくり」は、2つのゾーンに分かれているよ。
では、その様子を映像(写真)でたくさんお伝えしよう!
落ち着いてしばらくすると、年長さんがやってきた。
(年長A)
「また10の日ににもやってもらえない?
今日、幼稚園を休んでる子がいるの・・・」
(年中A))
「しあさってならいいよー!」
というわけで、しあさっての10の日も続くことになった。
********************************
一方、年長さんでは、「おかえししたい!」の声が・・・
こっそりと、打ち合わせが始まった!
【年長】卒業制作も佳境。
出来上がった作品が 園内のいたるところに、
飾られ始めています。
【年長】卒業式まであと10日になりました。
今年度もあと2週間ほどです。
年長児は、来週の15日(土)が卒業の日。
そこで、今日は、自分たちが迎える卒業式の
流れを一通り確認することにしました。
会場はこんなセッティングです。
雰囲気は「〇〇コレクション」といった風ですね。
【年中&年少】「ヒミツの〇〇パーティー」づくり。
年中児が主になって、卒業していく年長児へ、何か企画している。
「ありがとう」の気持ちを、「驚かせるプレゼント」で伝えたいらしい。
でも、「驚かせる」が、「ありがとう」になるだろうか?
しかも、その驚かせるには種類があるという。
ひとつは、「ワッ!」という、びっくりさせる驚き。
もうひとつは、「わぁ~・・・」という、ファンタジーな驚き。
そんな両方が味わえる「2つの迷路」をお部屋に作って、
年長児に楽しんでもらいたい!というのだ。
(パーティーは3日後を目指してるって)
なんて、素敵な発想なのだろう!
なんて、心がこもっているのだろう。
その「ありがとう」は、きっと、伝わるに違いない。
「ありがとう」の表現は、もっと、いろいろあるのだ。
【年中】「こうするといいんだ♪」
どろだんごづくりの方法の一つらしいのです!
Aくん「この紙(ティッシュペーパー)で包んで、置いておくといいんだ」
保育者「なんでー!?」
Aくん「こうするとね、すごく、固くなるんだよ」
(なるほど、周りをみると、何人かの子がやっています)
ティッシュペーパーをそんなふうに利用するとは!という驚きと、
でも、なんか、もったいなくも感じるなぁ、という思いが交錯・・・
保育では、こんな「子どもとどうかかわったら・・・」と、
葛藤する場面がいろいろ起きます。
そんなとき、目の前の事象(子ども)をよ~く見て、
かかわることが大切かなと思います。
【研修報告】幼稚園から小学校へ-子どもが主体の学校づくり-
「小学校が変わり始めた」と聞いて、
どのくらいが経過したでしょうか。
5年前、茅ヶ崎市の浜之郷小学校の実践を見たとき、
子どもと教師の関係性に驚きました。そして、
子どもたちが、実に楽しそうに学んでいるのです。
25年以上にもおよぶ この学校の取り組みは、
子ども、学校長、教師、保護者、地域、行政を中心に、
佐藤学氏を招いて 継続されてきたのでした。
これがモデルとなり、日本各地に広がっています。
その佐藤氏を招いたシンポジウム、
「対話的コミュニケーションとしての学び
『学びの共同体』の学校改革」が、
本日、東京大学福武ホールでありました。
氏は、「学校を一つつくること自体が難しい」と、
真に「協同する学び」を実践しようと改革する
学校の困難さを語っておりました。
ところが、それまで多くのアジア地域に見られた
一斉授業の形態が、韓国をはじめ、中国、台湾、
インドネシア・・・で、ここ数年、劇的に変わり始めた
というのです!(欧米はすでに変わっています)
日本でも同様かもしれません。すでに地域によっては、
「学び」の主体である子どもの声を聴き始めています。
それは同時に、子どもの「学びの地域格差」が
始まったとも考えられるでしょう。
そして、ここマエバシにも、学校改革に取り組んでいる
小学校(前橋市立山王小学校)があります!
(ご存知ですか!?内容はホームページをお読みください)
ここが「一つの小学校」となって、周辺に広がるといいと思います。
清心幼稚園でも、子どもが主体となって遊ぶ活動の中に
「学び」の姿をとらえようとしています。
主人公は子どもであり、それを支えるのが、
教師や保育者であるならば、小学校も幼稚園も
その役割はきっとかわらないでしょう。
そうすれば、幼稚園から小学校への接続も
さらにスムーズになっていくと確信しています。
【年長】何気ない遊びを見て思うこと。
雪解けのあと、園庭にのこった水たまり。
その水をくんで、一心に容器の中に注ぎ入れる姿がありました。
その水を山の上で、雪や砂、土とで繰り返し混ぜていました。
「もっと雪もってきてー!」 「この砂を入れよう!」
「うわ、あふれたァ!」 「なんか、滝みたいだな~!」
「水がもっといるよー!」 「もっと、大きい入れ物がいいんじゃない?」
何気ない、名もないこのような遊びが、結構面白いのです。
「もっと」「もっと」・・・と、次々に起こる変化を楽しんでいます。
子どもの表情が、それを物語っていますね。
単なる繰り返しのようだけど、素材や環境を生かし、
道具も使いこなしながら、遊びが継続する姿に、
未来の「主体的に活動する力」を見た気がしました。
2歳児のやりとりにほっこり。
お昼が近くなった頃、Aちゃんが涙を流していました。どうも、
お母さんのことが思い出されて、少しさみしくなったようなのです。
その様子に気づいた子たちが、声をかけていました。
Bちゃん:「だいじょうぶ?」
Aちゃん:「・・・・」(シクシク)
Cちゃん:「どうしたの?なんで ないてるの?」
Bちゃん:「さみしいんだってー」
(BちゃんがAちゃんのあたまをなでなでしながら)
Bちゃん:「あッ、ママねー くるから だいじょうぶ。ねー。」
Aちゃん:「・・・・」(コクっと、うなづく)
2歳児の、相手の様子に気が付いたり、感情を移入したり、
気遣ったりする姿に 気持ちがとてもあたたかくなりました。