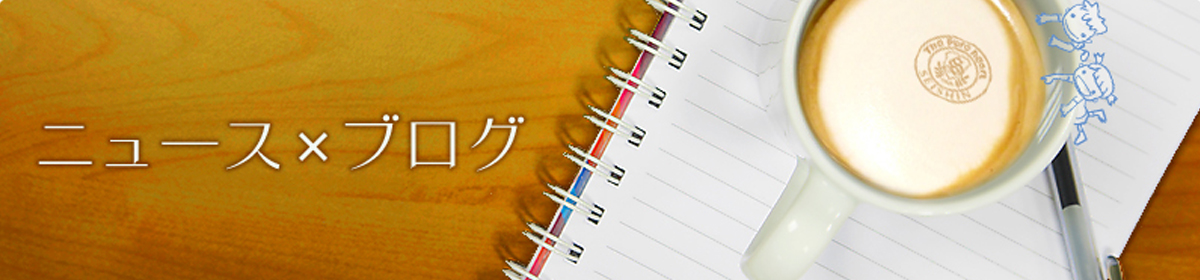5月13日(金)より、2017年度入園向けのプレ清心の
募集要項を配布します。
また同時に申込みの受付も開始いたします。
どうぞお早めにお越しください。お待ちしています。
【2017年度プレ清心の募集について】
■募集人数:10名(定員になり次第受付終了)
■募集対象:2017年4月時に2歳のお子さま
■受付開始:2016年5月17日(金)
■条件:満3歳児保育に編入します。次のことにご注意ください
・年少時から3年間通われる方に限ります
・空きがない場合は編入園時期が遅くなることがあります
■選考等:選考はありませんが、次のことを了解ください
・本園の保育理念に共感し、対話を重視する保育に協力してください
・幼児資料をもとに質問させていただくことがあります
■手続き:申込書、入園願書、幼児資料を提出してください
※詳しくは募集要項等でご確認ください
問合せ先:027-231-2415 (清心幼稚園)
======================
長らくお待たせしまして、大変申し訳ありませんでした。
5月13日は、幼稚園開放日にもなっておりますので、
あわせてお出かけください。
【第69回保育学会2016】「保育の質」を高める実践研究はどこへ
「保育の量」が足りないという一方、
「保育の質の最低限の部分」と、
「本当の意味での保育の質の向上」は、
どちらも切り離さずに考えたいもの。
保育が足りないと言って、急な拡大のしわ寄せで
命がなくなる現場では困ります。
しかし、そうした現状が国内で起きています。
それでは、もちろんいけないのですが、
「保育の質」に関する研究は、実践も絡んで
より多面的になってきたと感じます。
ただそれらは、〇〇式のように分かりやすい
早期的な教育ではないので、
評価や手ごたえが見えにくいです。
(ちなみに本園は、たとえば、カードを瞬時にめくって
記憶させる〇〇式や、高い跳び箱を飛ぶ等の〇〇式に
現時点で共感していません。そういう塾等も同様です)
だからこそ、エビデンスをもとにした地に足のついた
実践研究が必要ですし重ねていきたいと思っています。
園とご家庭で保育(教育)の方針が異なりますと、
対話が起こりにくくなりますので、これから
何かを選択されるようでありましたら、よくよく
お考えくださっていただけたらと思います。
(もし、早期教育や〇〇式等に関心がおありで、
そういったご家庭の教育方針があるようでしたら、
そうしたメソッドを導入している園もあります)
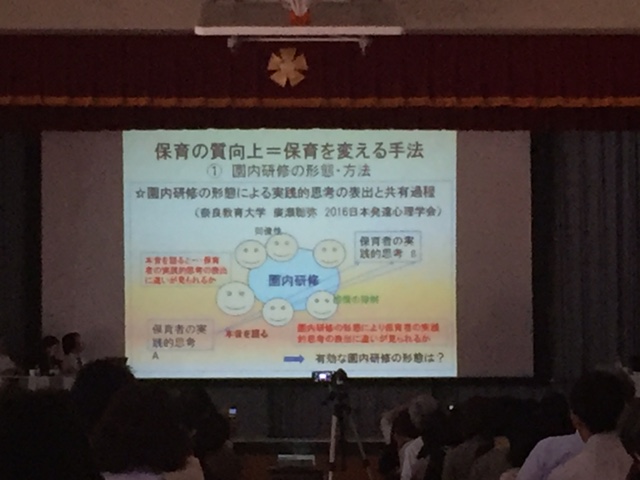
(今回の保育学会より@東京学芸大学)
「せなかにくっつける」(今月のワークショップ29)
■■■■■■■■■■■■■■■■
<せなかにくっつける>
■■■■■■■■■■■■■■■■
「今月のワークショップ」、りゃくして「こんわく」
次回は29回目になります。
===============
こんわく!は清心幼稚園で毎月行っている
子ども向けのワークショップです。
困惑しながら今月もわくわくするワークショップシリーズです。
小学生くらいから参加できます。
===============
■タイトル せなかにくっつける
■にちじ 2016年5月14日[土] 13:00~17:00
■たいしょう せなかがどこかものたりない人(小学生以上)
■もちもの せなか、すいとう、おやつ(こうかんしやすいもの)
■さんかひ 1,500円(材料費、おやつ代、保険代を含む)
■ばしょ 清心幼稚園(前橋市大手町3-1-21)
■もうしこみ FAX=027-233-0114
■メール=info@seishin-gakuen.jp(清心幼稚園)
■企画 中島 佑太(なかじま ゆうた・アーティスト)
【5歳児】もり土をした。土の中のジャガイモのために。

あるクラスの壁面。
こんな遊び感覚で飾られていました。
みなさんは何に見えますか?
園では保育者が壁面をつくるというよりも、
子どもたちの何かを飾ったり、
園生活の過程で何かを見せたりといった
空間(平面)の一つと思っています。
ところで、よくカラフルでカワイイ系の2頭身うさぎや、
くまが遊んでいる姿などを飾っている所もありますが、
アレってどうしてこんなに広まったんでしょう?
(「保育室・壁面」で画像検索すると・・・・)
子どもの個性を大事にしています、と聞く一方で、
保育室が画一化されている不思議。
そうならないように心掛けたいものです。
「ホームカミングデイ2016」のおしらせ
そつぎょうせい(しょうがくせい)のみなさま!
ひさしぶりに、ようちえんであそびましょう!
おまちしています!
**********************************
【ひにち】5がつ7にち(どようび)
1ねんせい:10:00~11:40
2~6年生:13:30~15:00
【ばしょ】せいしんようちえん
【れんらく】027-231-2415
【かかり】こんぴー、さわぴー、かねぴーほか
【第27回発達心理学会】@北海道大学
明日は5月というのに札幌は吹雪もよう。

寒暖差20度以上。

会場内は熱い。
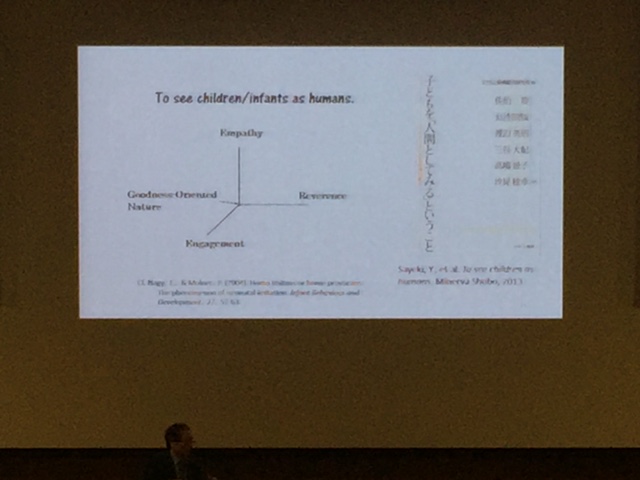
なかでも、佐伯胖氏とレディさんとのやりとり。
佐伯先生も熱かった。
【学会招待講演】
「なぜ社会的認知において「関わり合い」が重要か?」
●講演者Vasudevi Reddy
●指定討論者:佐伯胖
================================
ヴァスデヴィ・レディ 著 佐伯 胖 訳
『驚くべき乳幼児の心の世界
「二人称的アプローチ」から見えてくること』(ミネルヴァ書房)
(以下引用)
乳幼児はどのように人の心を理解するのか?
――この謎を解く鍵として本書が提起しているのが
「二人称的アプローチ(second-person approach)」である。
そこから、乳幼児が生後数か月で、すでに他者の
多様な心がわかっており、それらにきわめて
「人間的な」応答をしているという、従来の心理学研究では
描かれてこなかった驚くべき心の世界が浮かびあがってくる。
(原書:Reddy, V. 2008 How Infants Know Minds. Harvard University Press. )
[ここがポイント]
◎ 「二人称的アプローチ」という、人の心の世界に迫る新たなアプローチを提言。
◎ 従来の乳幼児の他者理解についての研究が見落としてきた、赤ちゃんの深い人間理解に根ざした、「ひとの心」の理解とかかわりを、あますところなく次々と明らかにする。
【4歳児】タケノコ見つけて掘った→食べたい
数日をかけて掘ったタケノコ。
キッチンスタッフの協力も得て、
昨日、ようやく煮るまで行き着いた。
保育室の中でひっそりと。
【5歳児】つくる。
【ひるごはん】ありがたいなぁ。
3歳以上の子どもたちが食べている給食。
(たむらやさんが届けてくれています)
今日は野菜がごろごろ入った豚汁。
これがあたたかいまま届く。
本業が「みそ漬け」づくりなだけに、
みそにも独特な手をかけているそう。
こういう毎日って、ほんとありがたい。