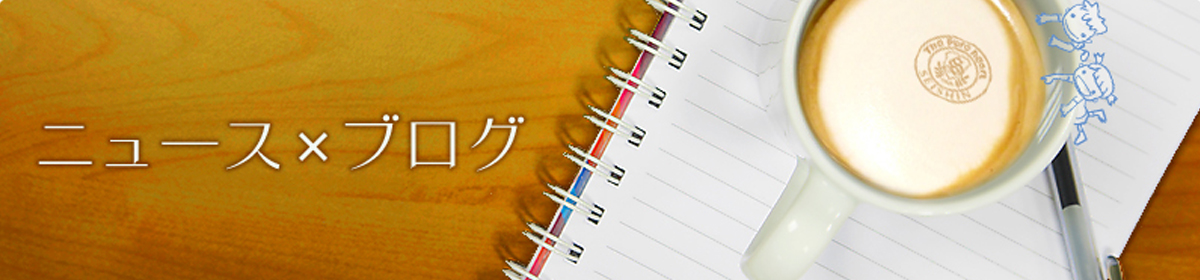みんなが入れるくらやみをつくろう!
というのが今日のテーマ。
4つのグループに分かれて段ボールと
クラフトテープで挑みました。
シンプルな素材とテーマ。
分かりやすさもワークショップのポイント。
多くの子どもたちは薄暗い中に入って作業。
多くの学生たちは周囲を補修。
分業が生まれるのはワークショップならでは。
でも、この分業は・・・どうしてだろう?
カテゴリー: こども(あそびの様子)
【5歳児】圧倒的。
■タイトル
■白い紙に絵の具(940✕368)
こういうところから始まる何か。
アチコチに散らばる名前のないモノたち。
彼らは、行き場がなくなると、ここに集う。
保育者の気の利いた発想がおもしろすぎる。
(もーいい加減にして!と言わない方法)
【4歳児】サイズを合わせて切る。
ながさの同じなモノをそろえたい、らしい。
そのために、自分の体の一部を使って測り、
手のひらの横の部分を線引きの代わりにして
線を引き、
・・・切っている。
非常にわかりやすい対話の状況。
モノとの対話、ヒトとの対話、ジブンとの対話。
ただ、切るといっても、やすやすとは切れないから
本人として、この状況は、かんたんじゃないだろう。
でも、それをやり続けてできているものが、ひとつ
となりに置いてある(ご覧いただけるだろうか)。
足が左右について、木枠のようになっている。
(これも長さを合わせるのに工夫してある)
だが、もちろんこれは木枠ではない。
「これ、なにつくったの・・・?」
「ん?とんねるー」
【年長】さつまいも調査。
どのくらい大きくなっているか、見に行ってみた。
9月にも1度とってみたのだが、まだ食べるほどの
サイズじゃなかったから。
では、今回どうなっていたかというと、
まだまだだったけど、前のと比べてみたら、
大きくなってた!
小さな畑かもしれないけれど、
行きたいときに行って、見て、確認して・・・
ってできるのがいい。
焼いもパーティーを計画中です。
【清心ピック】あんな!こんな!そんな!
清心ピックの参加の仕方はいろいろです。
たとえば何かのプログラムに出て参加する方法。
子どもたち、おとうさんやおかあさんだけでなく、
おにいさんやおねえさんも出られます。
おじいちゃんやおばあちゃんも出られます。
通園・入園されていない小さな赤ちゃんが
出られるプログラムもあります。
出場していないときは、見て参加することになりますが、
見ているだけでも、かなり楽しめるでは・・・と思います。
年少児が芝生の上でかくれんぼしたり、クルーズしたり、
年中児がダルマの伝統芸(笑)を考案したり、ミカンをとったり、
年長児がオイモやオナラをテーマに踊ったり、リレーしたり・・・
えっ!? 「かくれんぼ」???
何もないフィールドでかくれんぼ??
プログラムは「あれも!それも!これも!」という名前でしたので、
まさか、かくれんぼをするとは・・・と思われたかもしれません。
だから、プログラムタイトルから、どんなことかを想像してみる・・・
これも清心ピックの参加方法の一つでしょう。
そして、彼らを見て「そこ、かくれてないよ!」じゃないんです。
「3歳って、こんなに豊かに遊ぶんだ!」
これも、あれも、それも、かくれんぼなんだなぁーと見てみる。
(そうとらえていくセンスでぜひ!)
途中で出てきた箱を自分で持って行って、かくれちゃう・・・・
あー、もー最高ですね!
ふだんの園で遊ぶ延長なので、練習はありません。
雰囲気の違いがあっても、自然体でいられるのは、
そうしたことにもよると思います。
一つひとつのプログラムに、その背景や
プロセスがあります。
あんな、こんな、そんなことをいろいろ想像して
見ていただけると、またひと味違って参加できる
かなと思います。
【年長】清心ピックでオペレッタをやってみること。
演じる、見せる、伝える・・・って難しいことだと思う。
例えば、こども園の「教育・保育要領」には、
指導の事項として、感性と表現に関する領域
「表現」という項目がある。
その解説書(結構下の方です)を読むと、
大切にしたいことがたくさん書いてある。
それが、子どもたちがオペレッタを作っていくことと
「生きる力の基礎となる、心情、意欲、態度」と、
どう絡んでくるかは、また難しいことだなって思う。
いつもの園生活と違うような、違わないような・・・・
やりこみ過ぎて、練習になるとかは、もちろん論外!
保育者などオトナが衣装を作るとかも話が違う。
(そこにはオトナの自己満足が溢れている)
その体験の中の一人一人のプロセスをしっかり
見ていくことが必要だし、大切だ。
今日の前橋公園でのリハーサルっぽい感じが
子どもの体験の一つになっているだろうか?と。
それらの意味がなくなったとき、このオペレッタは
なくなっていくし、清心ピックからも消えるだろう。
なんとなく続けるものではないのだから。
【年中】いっぱいの・・・
なつみかんとか、ぶどうとか、ももとか、
わかめとか・・・
もうなんだか、どんなつながりか分からないけど、
いま、保育室にたくさん下がっている。
どうも今度の清心ピックの競技で使いたいらしい!
しばーらく、子どもたちが作り続けているので、
こんなにいっぱいになった。
たくさんあると、いつもの保育室の風景も
違って見えるからおもしろい。
これら・・・なつみかんのモチーフは、今年、
やっとの思いで「収穫したあのなつみかん」!
ちなみに、この競技名は、
「おとせ!さがせ!たくさんとるぞ!」
【年長】前橋公園で。
サンザシの仲間かな?
公園の周辺に、最近よく生っています。
採った実は手で集める・・・・では足らず、
帽子やコップを入れ物代わりにして・・・
それから、ごっこ遊びが始まりました。
昔も今も、実などを採って遊ぶあそびって
変わらないものですね。
「はなのミツ!」って言ってチューチューしたり、
口の中や周りを赤くしたり・・・ね。
わな!?
昨日、前橋公園に遊びに行った、4歳児と2歳児たち。
天気も良く、トンボたちがたくさん飛んでいました。
そうなると、ひとつでも捕まえてみたくなるもの。
ビニール袋をもって、走って追いこむのですが、
相手は、すいすーいと高く飛んでいってしまいます。
すると・・・ある考えが浮かんだらしく・・・
公園の中央に、よいショっと、折れ枝を差し込みました。
それから、そこから、ずーっと離れて、じーっと見ているのです。
トンボがあの枝に止まったら、捕まえに行くのだそう。
結果は・・・