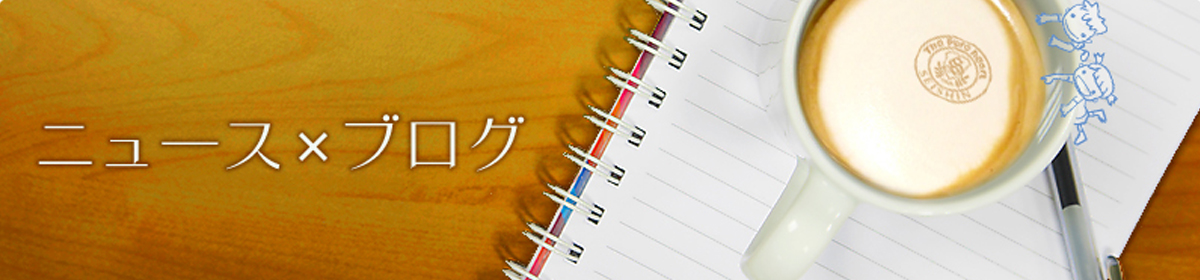廊下や プレイホール、ホール、いろいろな所で一緒に遊んだんだ。
年少さんのお部屋にもやってきたんだ。
ふしぎな楽器もいっぱいあったよ。
なんて、おもしろい音なんだ。 これは。
近いうちにまた遊ぼう、って約束をしたよ。
カテゴリー: こども(あそびの様子)
【年長】「キャンバス」の「なまえ」を考えた
キャンバスに 作品のタイトルをつけることになって 数日がたった。
いくつかの候補があがっているが、そこから なかなか決まらない。
なぜなら、多数決で決めていないのだ。
それぞれが、イイという「なまえ」に理由があった。
この前は、自分の「なまえ」がどうしてついたのか、という話になった。
そうしたら、「なまえつけるの、むずかしい」って。
本当に納得のいく「なまえ」がつくか、もう少し待ってみよう。
【年少】石に色を塗って・・・
昨日の様子・・・
気に入ったところに お気に入りの色を塗っているようです。 とても器用に。
1日あけて、その続きが始まりました。
少しその輪が広がっています。
そのうちのいくつかに ニスを塗って、乾かして・・・
こんな風に飾られました。
【年少】園庭の山の上に・・・
ねころがってみる。
いろいろもってきてみる。 そして、ならべてみる。
*************************************************************
何気ない遊びの様子。
でも、この過程をみると、友だち関係の中で遊びを
協同していることが分かります。
これだけのものをここに運んでくることも
なかなかのことだと思います。
*************************************************************
満3歳児保育始まります。
清心幼稚園が、満3歳児の保育を始めます。
今までの「プレ清心」を拡大する形で行います。
つきましては2013年度の新入園児を募集します。
関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。
■満3歳児保育■
*保育時間
(午前保育の日)9:00~11:00
(午後の保育もある日)9:00~13:10
*独立した保育室です。
*担任がつきます。
*納付金は現在の在園児と同じです(ホームページでご確認ください)
*就園奨励費の対象になります。
■2013年度の「プレ清心」■
・新年度からは、満2歳児クラスになります。
・満3歳児と一緒に過ごします。
・週2日(月水クラス・火木クラス)の開催です。
週4日の通園も可能です。
・週2日で月額8,000円。週4日で月額15,000円。
何かございましたら、事務局までお問い合わせください。
イワシのカラダはどこへ?(節分番外編)
イワシのアタマは、節分用の「ヒイラギイワシ」になりました。
では、カラダはというと・・・
木切れを燃やして、
木炭に火を点け、
七輪で焼いて、
ひとつまみずつ 分け合って いただきました!
気持ちのいい豆まき。
園庭に とつぜん現れた!
年中さんや年少さんが準備していた「ひいらぎイワシ」や福豆の買出しを
遠目に見たり聞いたりしていた 年長さんの何人かが変身。
「おにはー そとー!」 「ふくはー うちー!」
オニも負けていません。 豆を拾って、すぐさま投げ返します。
あっ、2階のベランダからも豆が飛んできた!
【年中】豆まきの準備をする②(ひいらぎイワシを作る)
園庭でイワシをさばくことになった。
なぜなら、イワシのアタマが必要なのだ。
イワシをよくみてみる。 そして切ってみる。
そのアタマに、普段遊びで使っている木切れを 刺してみる。
ヒイラギの葉が見当たらず、 代用品を見つけてきたのだ。
できあがったものをこんな風に並べていた。
これから、どうなるのかなァ、と思ってみていると、
保育室の前に砂山を作って、各部屋ごとに立てていた。
こうすれば、きっと鬼も部屋の中には入ってこないだろう。
なかなかの思いつきだと思った。
【年少&年中】豆まきの準備をする①(豆とイワシの調達)
年中の子どもたちから、鬼を追い払うには 「豆とイワシが必要」との話がでた。
「じゃあ、買いに行こう!」と、年中さんと年少さんが協力して出かけることに。
そこで、豆チームは、「フレッセイで売ってる」と、フレッセイ(スーパー)へ。
一方、イワシチームは、魚屋(「魚健」さん)へ。
途中、道が分からなくなって迷っていると、秋葉写真館の秋葉さんが
地図を見ながら教えてくれた。
「魚健」さんに着くと、イワシを買いに来たはずだけど、
子どもたちは いろいろな魚たちに興味津々。
子どもたち:「これなに~?」(アサリを見つけて)
すると、おかみさんがいろいろと見せてくれた。
子どもA:「あっ、いま、水みたいの でた!」
おかみさん:「生きているんだよ」
子どもA:「ちょっとさわりたい」
子どもB:「ぼくもー!」
子どもC:「これあいてる、なんでー?」
おかみさん:「そうね、これもあいているよ」
すると しばらくして・・・・
子どもD:「ねえー、はやくサバを買って もどろうよ」
子どもたち:「えっ、サバ??」
子どもD:「そうだよ、サバだよ」
子どもA:「ちがうよ、イワシだよ」
しばらく「サバ」か「イワシ」かの相談。
話し合いの結果、「イワシ」を5匹買って帰ることに。
帰り際、「何か聞いておきたいことある?」と保育者。
子どもE:「どうやって、ぜんぶの魚を止めてるんですか?」
おかみさん:「そうだねー」と、魚の〆方を教えてくれた。
おかみさん:「難しかったかな? 分かった?」
子どもE:「うん!」
********************************************************
確かにちょっと難しい話しだなァって、思いながら聞いていた。
でも、「魚の〆方」が分かったかどうかが 大事ではないのだろう。
子どもが、自分の経験や 知っている言葉を総動員し、
「魚と対話」するからこそ、「ぜんぶ動いていない」
「どうして止まってるのかな」 「なんかおかしいな」って気がつき、
〆ることで「止まる」ってことが分かったんだと思う。
こうして実感を得ながら 納得していくことが、
より意味のある「学び」になっていくんだろうな。
「もちつき⑥」食材を準備する(あんこをつくる)
ホールではあんこづくりが進行しています。
明日の本番を控えて、もち米をすすいぐ準備も進みます。