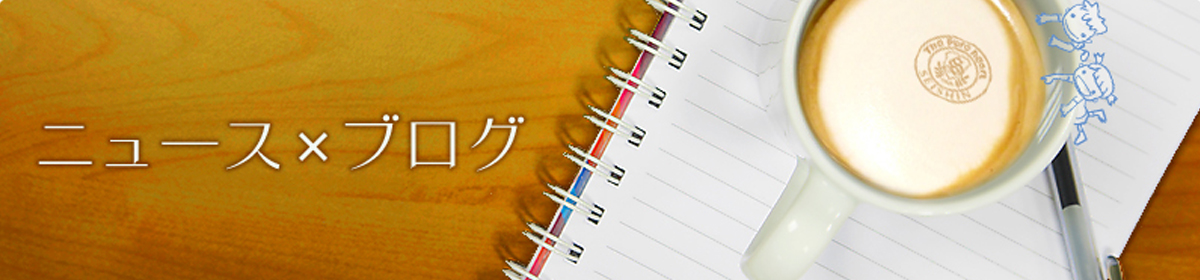やってきました!3回目(一昨日の様子です)
今回は、コンドルズさんたちと一緒にワークショップを
体験してきた群馬大生もプレゼンしました。
学生さんにとっては、教育・介護実習、ボランティア活動以外に、
実践の場が多くないので、こうした講義のある教員養成校が
増えるといいですねー。
身体系ワークショップは、言語表現とは違って、
コミュニケーションがとりやすいので、即興的に
広がっていきます(〇〇になってみる)。
一人から二人・・・そして、・・・大人数へ。
これまでの一緒に遊んできた経験の共有もあってか、
今まで以上に全身がアクティブな状態です。
表現するって本当に豊かなんだなァ。
今日の終わりは、こんな遊びゴコロで。
「よ~し、落とさないように、ハイタッチに行ってみよー!」
ちょっとした工夫で こんなふうに楽しめちゃうんです。
コンドルズ、やっぱりいいですね!
カテゴリー: こども(あそびの様子)
【年少】前橋公園で。
おいかけっこをしたり、
秋をつかまえたりしてみる♪
【育てる】まいた!
数日の間に、ブロッコリーの苗を植えたり
小松菜の種をまいたりしています。
時期がぎりぎりなので、芽が出るかどうか・・・
しょうぼうしゃもきた!
避難訓練をしたら、消防車と、消防隊もやってきました。
せっかくなので、近くまで見に行きました。
興味の湧くことがいっぱい♪
前橋消防署のみなさま、どうもありがとうございます。
【年長】畑の引っ越しが終わり・・・
畑で何を育てたいか相談しました。
それから、種や苗を探しに町の中に行くことになりました。
園では、こういうことが起きそうなことを想定して、
たとえば、先輩たちが使っていた地図を保育室に
貼っておくなどしてあります。
子どもたちは、そのコンパクト版を持ちながら、
今回の目的地を目指したのでした。
知ってる!という子どもの自己申告を先頭にして
歩きはじめましたが、そう簡単に見つかりません。
ようやく、道路の向かい側から「あっちにある!」と発見。
でも、お店の方に聞いてみると、ここに種や苗は
置いてなかったのです。
ひとまず、持ってきた地図で、今の場所を確認しました。
ところが、自分の感覚はそれぞれにあって・・・
「こっちからきて、あそこわたって・・・」
「でも、そこでまがったでしょー」
(以前、先輩たちも行ったことのある)
別の花屋さんに向かうことになるまで、
単純にはいかないのです。
「だから、そっちじゃなくて、あっちでしょー」
「どっちもいけるんじゃない!?」
「こっち、ちかみちとか!」
さらに、途中で、道を教えてもらって・・
「あ!たねってかいてあるー!!」
「どこー?」
こうして、なんとか探すことに成功したのです。
(もう刑事ドラマみたい!)
ところが!
なんと、臨時休業の張り紙が。。。。
(この辺りまでは、保育者も想定内なのですが)
すると、「ちがう とこ、 しってる!」という声があがって、
「わたしんちのまえにあるからだいじょうぶ!」と言うので、
もう1軒ハシゴすることになったのです(いや~ドラマだ)。
とうとう3軒目・・・でも、ここにもありませんでした。
(大人でも、そういうこと・・・ありますね)
*******************************
そして、がっかりして園まで帰りました・・・で
この日の話は終わらなかったのです。
どこを通ったら幼稚園まで帰れるか?で意見が分かれて、
どんなに相談しても、まとまりません。
でも、それも分かります。これだけいろいろ歩いてきたら、
方向感覚や空間認知が、あやふやになってしまうことも、
きっとあります。
私たちも、「じゃあ、別々に行ってみる?」と聞いてみると、
子どもたちも、「そうしよう!」と。
そして、たがいに「そっちじゃないよ!」という気持ちで、
(実際にそう話している子どももいましたが)
二つの方向(逆方向)に分かれて、出発しました。
どの道を選択するか?って、すごいことですね!
ただ、このケース、聞いていると、どうも根拠があって、
道を選んでいる子が多いのです。
「この道は パパが仕事行くとき 通ってるー」
「あっちに行くと・・・〇〇があったかなー」
「・・・しらない。通ったことないし」
「朝、幼稚園いくとき、こっちとおってる」
たいていは、保育者(大人)が「こっちだよ」って、
教えることが多いと思いますが、いかがですか?
保育にもいろいろな向き合い方がありますね。
最後までハプニングの連続の中で
すごく驚いた(感動した)のは、
どちらも、工夫して園までたどり着いたということ。
そして、もうひとつは、
「あっちはようちえんにかえれるかな・・・」と、
互いにもう一方を案じながら歩いていたということです。
子どもたちが、それぞれ主体的に考えて
行動するプロセスには、折り合いがつかないことも
たくさん出てくるけど、内面的なつながりや、
思いやりがないわけじゃないんですね~
(さいごまでドラマだァ)
【年長】コンドルズとあそぼう!②
コンドルズや群馬大学の学生さんと一緒に、
身体を使って遊ぶシリーズ(全5回)。
初回(9/2)は、おうちの方も体験していただきました。
今日からさらに遊んでいきます(第2~第4回)。
こんなことや、あんなこと・・・
2人、3人、4人・・・
「○○になってみる」が起きて・・・
そのアイディアも、やってみるアイディアも、
即興的な仲間の中から出てきたもの!
これから、毎週一緒に遊ぶ予定です。
果たして、子どもたちの中に、私たちの中に、
コンドルズさんや、学生さんたちの中に何が起こるカナ?
そして、子どもにとっての意味は・・・?
私たちも体感しながら、レポートしたいと思います。
【年少】いっしょにやってみる。
いっしょにやると、できることがふえるね♪
(カキの実を採り終えて)
【年長】ハロウィンということですが。
いつからか、日本でも、ハロウィンが、
目につくようになりました。
子どもたちにとっては、生まれたときから
この光景なので、不自然さはないのでしょう。
そして、子どもたちのイメージの一つは、
やっぱり、かぼちゃなのです。
かぼちゃを近くの八百屋で購入してきた、年長児たち。
本日、それをみなで食べるべく、切る、煮る、包む、配る・・・に
とりかかったのでした。
【年少】友だちとかかわりあって育つ。
「アイスクリームでーす」 「いらっしゃいませー」
「アイスクリームやさんでーす」
不特定の誰かに届くか届かないかの声で呼びかけながら、
なりきって遊んでいる(ごっこ遊び)年少児たち。
色づいてきた落ち葉を、砂場用のジョウゴに入れて、
かきまぜたり、つぶりたしして、それを作っていました。
作り方も、声のかけ方もそれぞれに違うのですが、
3人とも「アイスクリーム屋さん」のようです。
こうして、一つの遊びを、ゆったりと共有しながら、
やっていると、いつの間にか、隣の誰かの
アイディアが足されて、より複雑になりますね~
この時期の3歳児は、遊びの場と時間をともにしながら、
新たな友だちと小グループになったり、離れたりして、
かかわりがより複雑になっていくので、楽しいことも増えますが、
トラブルになることも増えていきます。
でも、それが幼稚園生活のいいところ。
(ココではそうした育ちがたくさん起きます♪)
今、すべてが受け入れられなくても、
少しずつ、少しずつ、そうしたことに向き合っていく
チカラに変わっていくのです。
【遠足】県立自然史博物館へ行ったよ!
清心幼稚園が、こちらに行くのは初めてです。
県内ではかなりの人気で、幼稚園、保育園、
小学校・・・と多くの学校が利用しています。
恐竜の化石の展示をはじめ、大人も学び甲斐のある
施設になっています。
今回は、久しぶりに、年少、年中、年長と
全学年が行ってきました。
年少&年中はおうちの方と一緒に見てまわり、
年長は子どもだけのグループで探検♪
年長児くらいになると、じっくり見たくなったり、
興味の対象がだいぶ違ってきたりしますね。
だから、5~6人の小グループになって、主張が
ぶつかることも想定しながら、活動します。
そうすると、「一通り見てまわる」のではなく、
一つひとつと向き合う姿が増えてきます。