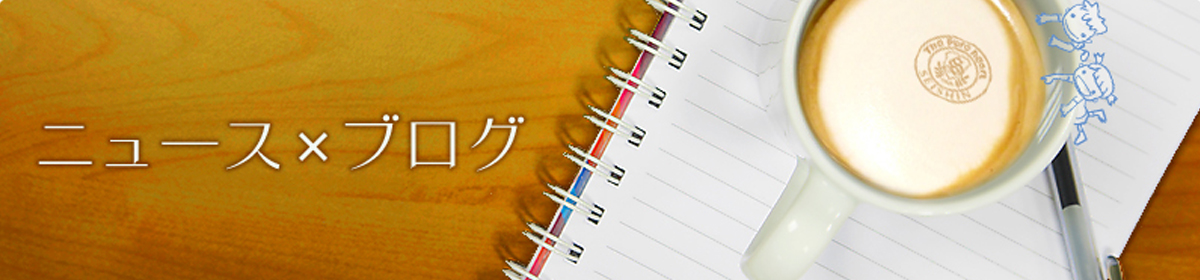幼稚園生活を振り返って、表現したいことを形にします。
素材、モチーフ、道具も決まってはいません。
その意味では、ちょっと大変さもあるかもしれませんね。
カテゴリー: こども(あそびの様子)
この日のドミノ②
いや・・・ちょっとまって・・・これは・・・ドミノだろうか・・・
あのときの年長児たちを横目に見ていた、
年中児と2歳児による、別の遊びかもしれない・・・
いや、やっぱり、ドミノかもしれない・・・
【年長】シンプルな遊び。
ゴムと割り箸、それに的さえあれば、すぐにできる遊び。
的あてゲーム、それとも射的というのかな。
ところが、この遊びは、競技性もあって、
シンプルなのに奥が深いようだ。
まず、ゴムの太さや長さ、強さが違っている。
(園にあるゴムは製造メーカーが複数)
だから、道具(割り箸)も、それぞれが工夫して作ることになる。
そうなると、使い方や飛ばし方が違ってくる。
ときには、隣の技をこっそりと取り入れることだってある。
だって何より、誰より、一番に、あの的に当てたい!のだ。
そして、いろいろな保育者に、「いいゴムない?」と聞いて回り、
偶然、手に入れられることもあれば、収穫がないこともある。
そんなことで、1日や2日でこの遊びは終わらず、
続いている。
豆まき用の豆さがしへ。
4歳児と3歳児の何人かが、豆まき用の豆を探しに、
出かけました。
(「ここ、なんだろうーねー」とか見上げつつ・・・)
全員で行かないのは、鬼になりたい!と、変装や道具を
鬼ルーム(通称)で作っている子もいるし、
豆の必要感がそこまでなかった子もいたからです。
(中途半端に行くと、事故に遭う危険も高まります)
いつもの須田商店にあるかもしれないし、さらには、
八百屋さんにもあったという情報を得た一行は、
まもなく、信号機のある横断歩道を横切りかけました。
すると・・・その信号が偶然、青に変わりました。
それを見つけて「こっちだよ!」と、一人が言いました。
「そうだねー」と数人がすぐに同調。
「信号が青になる」⇒「そっちにいく」
(このあたりが、直結なようです)
さらに、様子が変わってきて・・・
「この信号を渡ってあっちに行く!」
それ自体が目的な風に・・・
そこで、保育者がいったん整理しつつ、
改めて、これからのことを確認します。
目的を取り戻したメンバーは、改めて須田商店を目指します!
さっきのことがなかったかのように、足取りも早く!
行く先に向かうエネルギーが、少し強くなったみたいです。
須田さんに会うと、早速、店内中で豆さがし・・・
ところが、どうも、量が足らないみたい。
寒いし、お腹も減ってきたし、帰ろうか?
という話が出てきたかと思ったら・・・
「やっぱり、やおやさん、いくー!!」
そこで八百屋さんの場所をチェックしました。
でも、地図と実際の感覚は合わないらしく、ひとまず
目印の建物(元気21)を目指して歩くことになりました。
これからどうなる⁉と、保育者たちがヤキモキし始めたころ、
「ねえ!あそこ!みてー!えががいてあるー!」と。
このとき「ホッ」としたのは、保育者だったでしょうか・・・
子どもたちは、ヤッタゼ!といった感じでした。
意気揚々と帰ってきたのも、きっと、ご想像いただけるでしょう。
新たな素材をアトリエに出したら・・・
それを使って何かを作る、ではなく、
別なところに運んで行って、
「いろいろなものをうってるみせ」になっていた。
この日のドミノ。
この前とはまた少し違った感じでしょうか・・・
このところ、見ているだけで、にやにやしてしまいます。
(現代アートを見る感じがするのは気のせいでしょうか)
おもちつきの中で起こるいろいろなこと(昨日です)。
まずは、火おこしから!
(ここでは、これも大人だけの仕事ではありません!)
もちろん、もちつきは自分たちですが、
もちをちぎって、食べやすくすることや、
味付けなども、分担してやっています。
5歳児が係りを割り当てられてやるのではなく、
「(わたしは)〇〇をやる」という波及が
4歳児に伝わって、受け継がれていきました。
そうした中、お姉さんが、自分よりも小さい子に聞いて、
手をひいている姿がありました。
今日のように、多くの人が行き交う公共の場で、
周りに気づいて、行動するって普通なことだけど、
どこか躊躇したり、行動しなかったり・・・
ごく自然と出てくる、こんなふうになりたいですね。
ホウレンソウをたっぷりと入れた、お雑煮用の汁も、
できあがりました♪
昼食の時に合わせて、大いに振る舞われましたとさ。
おもちつきの日の準備を少しずつ。
もち米を洗っておくとか、
雑煮用の出汁をとるとか、
小豆を煮て、あんこをつくるとか、
野菜を切ったり、切っているところを見たり、
それを教えてもらったりとか、
こんなチラシが作られたり、配られたりとか、
今年もきな粉ができあがったりとか・・・
けずる(雑煮をつくりたい⇒鰹の削り節)
削り節がたくさん必要だ。だから、時間がかかる。
なんでも簡単に手に入るわけじゃない。
毎日、少しずつ削れていく(できあがっていく)。
じーっくりと、かかわる子もいれば、
最初のときだけ!っていう子もいる。
(どっちがいいとかじゃないデス)
削り節のなんともいえない香りが
数日にわたって保育室に漂っている・・・
そういう保育の環境にしておくと、それが、
「子どもの身近なモノ」になっていく。
だから、そのかかる時間も大切したいのだ。
外にでてきた「ピタゴラ」。
金曜日の昼下がり。遊びの残骸が・・・
いや、続き!!
どうやら、側壁が一部ついているようだ。
この前の⇒ピタゴラ報告。