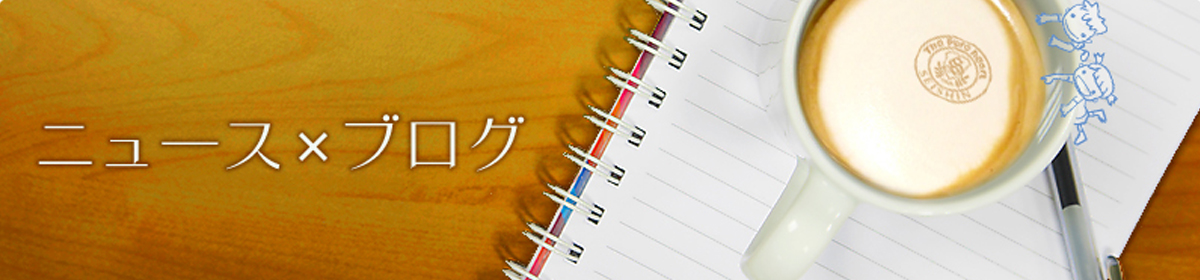ベッドにお客さんが寝転ぶと、早速、ひざ掛けのサービスが。
首や頭の居心地をみたり、顔の上にかけるアレ
(布とか不織布のようなやつ)をのせたりして・・・
髪を丁寧に洗っていました。ここは美容院かな。
どこかで見てきたのでしょうか。それとも、
してもらったことがあるのかな。
洗い終えると、体をゆっくりと起こしてくれます。
お客さんも、スタッフもとても楽しそう。
この美容院、しばらくすると、設定が少し変わって
歯医者になっていました。
こんなふうに柔軟に遊べちゃうところが
またおもしろいですね。
カテゴリー: こども(あそびの様子)
こんな滑り方もある!?②(ん!こんどはなに?)
先日、滑り台で遊ぶ姿(1月28日付ブログ)を紹介しました。
今日は、室内でこんな光景を見かけました。
・・・階段で・・・年長児たちが・・・・・
やっぱり何度も滑って遊んでいたのでした。
最初は、ボールを滑らせて楽しんでいたようですが、
結局、自分たちを滑らせちゃっていました!
こういうとき「身体を通した遊び(対話)」っていうのかな?
「明日もやろう!」と言いながら、滑るやつ(段ボール)を
しまっていました。
節分の1日をいろいろに楽しむ。
まずは、豆まき。子どもたちが炒った大豆です。
年長児の有志+カメラマンが鬼の役をかってくれました。
そのあとは、年中さんによる お茶やさんで一休み。
豆茶が振る舞われていました(炒りたての豆+熱いお湯)。
昼食には、恵方巻きを作って食べる子も。
保育後アート(年長)では、「おにのえほん」づくり。
(「こわいおに」と「かわいいおに」をかいてみよう)
伝統的な慣習に、最近の風習が加わって、
節分の風景も変わってきてるように感じます。
【親子で雪遊び】@志賀高原焼額山スキー場
今日からもう2月!1月が、あっという間に過ぎました。
そして・・・本日は、親子(希望者)で行く雪遊び。
「だるまさんがころんだ(雪上親子ver.)」などのゲームをしたり、
スキー体験をしたり(まずは、片方の足でやってみようか!)。
子どもたちがどんどん上手になるのは、
何でも共通かもしれませんね。
「また、やりたい!」という声があって、とても嬉しかったです。
来年も企画したくなりますね。そのときは、ぜひまた行きましょう。
(焼額山ゴンドラから岩菅山を望む)
とても穏やかな1日でそれもよかったです。
【年長】こんな活動(遊び)も・・・
(「おさいほうの基本」という本を見ながら)
「こんなふうにやってもいいかもねー」
そんな保育者の姿を、子どもが見られると、何かになる。
どんなふうに「見せるか」は、保育者の関わり方(ウデ)の一つだと思う。
(「マフラー」を編む)
そして、その空気感は、こんなふうに伝染していくのだ。
【年少&年中】昨日も、節分の話が続いて・・・
「お豆を火でやって(炒って)から投げる」とかの話が出てきました。
そこで、今日は、節分用の大豆を買いに行くことになりました。
1月は、もちつき用の食材を調達するため、
・きなこ用の大豆とあんこ用の小豆:須田商店(麹・米・大豆・とうふ他)
・のり:鳥山海苔店(のり・コンブ他)
・のり:大和園(お茶・のり他)
・もち米:籾山米穀店(米・弁当他)へ買いに行きました。
その経験に加え、日ごろ子どもたちが行っているのかな?
子どもからスーパーやデパートの名前も出てきました。
そこで、まずは地図を見ながら須田商店を探しました。
それから13~14人のグループに分かれて出発しました。
通る道は、グループごとに決まるので、いろいろです。
パン屋さんで道を聞くグループや、前の記憶を思い出して、
「このラーメン、前もあったからあってるね」と確認しながら
歩くグループなどそれぞれでした。
(このお店の雰囲気がいつもいいです)
(須田さんの表情も、またいいのです)
「豆が見つかるかな?どこにあるかな~?」
「豆をよ~く炒って、熱いお湯に入れると、体にいい豆茶になるよ」
「煮てもいいしね~」
須田さんは、あの表情で子どもたちに話します。
そして、須田さんは、よく笑います。
こういう場所で、こういう方に、こんな話を聞く・・・
これこそ、人間の文化の伝承(循環)だなって思います。
須田さんが、楽しそうに話をしてくれて、
この前の鳥山さんも、楽しそうに話をしてくれて、
子どもたちが、そんな大人の雰囲気を感じて、
大きくなっていく町もいいんじゃないでしょうか。
みなさんの周囲には、どんな方がいらっしゃいますか?
保育では、ときに地域の方にかかわってもらうと、
子どもの対話する世界が広がるなァ、と実感しています。
こんな滑り方もある!?
先日の日曜日、滑り台を使った遊びについて少し書きました。
そんな矢先、こんな風に遊んでいる姿が(年中さんたち)ありました。
いろいろにしながら、何度も楽しんでいる様子が印象的でした。
(マットを持ち込んで、3人で滑ってみる)
(滑ってくるところに、下からも上がっていってみる)
ここには、それぞれの子どもの中に、体験の積み重ね、
それこそ「経験」があると感じます。
でも、こうしたプロセスをどんな活動で、どのように得るかは、
園の内外に、家庭に、そして地域の中に、多様にあると思います。
「この経験をしなければならない」というのではなく、
子どもにとって意味があり、実感を得る体験が、
きっと大切なんだろうなと、改めて考えるのです。
【年少&年中】節分の日をどうするか?
年長児は保育開放日の振替休日でお休み。
今日は、年少と年中だけなので、いつも以上に園内広々。
そんな折、近づいてくる節分について、どうしようか
年中さんと年少さんとが話しあっていたようだ。
「〇〇で豆を買ってきたい!」 そんな話も出ている。
今後の彼らの動向に要注目だ。
【年長】「保育開放日」を行いました。
今日は、年長さんの「保育開放日」でした。
保育開放日は、親子で結構本気になって 遊ぶ日です!
だから、こんな風景が園内のアチコチで見られました。
さらに、前橋公園に行って、ドロケイ(ケイドロ)やリレー、
かくれんぼをして遊びました。
これだけ動いても、エネルギーが衰えない子どもたち。
お家の方には、子どもの育ちがより実感できる日だと思います。
■コレってなに?■
***** 「 保 育 開 放 日 」 と は ? *****
子どもとお家の方とが、一緒に園生活を過ごす日のこと。
年に1回(土曜日)を予定している。お家の方にとっては、
遊びを通して子どもと関わりあいながら、子どもの凄さや
育ちを体験しながら知る日でもある。真剣に遊ぶことの
気持ちよさや奥深さを感じることができるといいですね。
ちなみに「保育参観」は年3回(平日)。
縄(縄跳用のロープ)を使った遊びの広がり。
鉄棒に縄の両端を結び、ブランコ風にしてみたり、
アスレチックに巻きつけたりして 遊ぶ姿がよくあります。
縄を使った遊びは、安全面の配慮が大切ですが、多様な工夫が生まれ、
おもしろい遊びが次々と起きます。職人のように扱う子も現れて、
周囲からは一目を置かれているようです。
さて、こちらは、先週の1月17日(金)。
バケツに土を入れて、それを引き上げる年長児たちです。
穴掘りの穴が深くなりすぎたので、生まれた作業方法です。
(今や頭上の遊具と合体。釣瓶(つるべ)のようになっています!)
そして、今週に入った1月22日(水)。
年中児がそれを見て、別の場所でいろいろとやっていました。
本日、1月24日(金)。
ドロ水を入れたバケツをズリズリと運んだり、
ネット遊具からタイヤを吊り下げて、乗って遊んでみたり、
木の幹と幹の間に縄を渡して、釣瓶のようにしてみたり。
こんなことが、同時多発的に 起きています。
保育者たちは、四方に神経を使って見守っているのですが、
「(こうしばると)あとで、とれなくなるからよくない」とか、
「(こうすると)うまく結べる」とか言いながら、当の子どもたちは、
大人の想像以上に「縄」を使いこなしています。