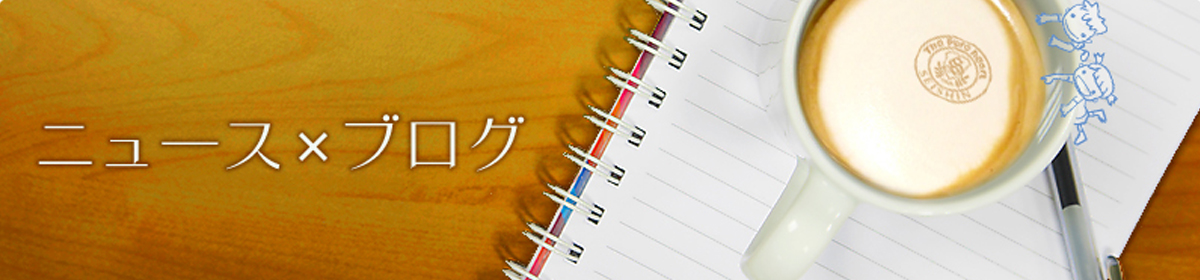カテゴリー: こども(あそびの様子)
「今、たいせつにしたいこと」(6月のおたよりから)
「6月のおたより」で、2歳児クラスの保育者が
ご家庭向けに書いていた話を紹介します。
2,3歳くらいのお子さま、保育に通い始めのお子さまを
子育てしている方に、きっと参考になると思います。
(もしかしたら、お悩みがひとつ解決するかも!)
*****************************************
【今、たいせつにしたいこと】
“おともだちと遊べていますか?”
先日、あるお母さまのそんな思いを耳にしました。
同世代の子への関心が芽生え、一緒に遊ぶようになって
くるのはもっと先の話かと思います。
まず、この時期の子どもに大事なことはいろいろと
遊びはじめることです。(ですから、今はお子さまに
友だちづくりをあまり求めないでくださいね)
2,3歳くらいまでは、「一人あそび」が主となる活動であり、
並んで一緒に遊んでいるように見えても、子どもたちは、
それぞれのイメージの中で遊んでいることが多いです。
今は、一人ひとりが、その子らしく遊びを始めて、
それを十分に遊ぶ中で、自分の好きなことを
見つけられたら、いいですね。
私たちは、その子どもが興味をもってやっていることを
“なにをしているのかな”と、少し離れて見守りつつ、
“どういうことが好きなのかな” “なにがやりたいのかな”
と、一人ひとりの遊びの中で、子どもの関心がどこに
あるのか、毎日把握しているところです。
遊びが楽しいと自覚するのもこれからですから、
お家の方にも、何かあればそれを受けとめ、
声をかけ、一緒に遊んでみるスキンシップを
大事にしてほしいと思っています。
(ここまで抜粋)
*****************************************
幼稚園や保育園で出会う、同年代の子ども同士で、
楽しく遊べたら・・・と、願いたくなる気持ち、とてもよく
分かります。
でも、友だちができるって、簡単ではないのですね。
まったく知らない者が出会って、仲良くなる・・・・
私たちも、初めて会った人とすぐ仲良くなれるでしょうか。
人見知りする場合もあるかもしれません。
“隣の子と何か一緒にしたいな!”
そんな気持ちが起こり、隣の子もそういう気持ちで
応じてくれた時、友だち関係の芽生えがあるのでしょう。
【年長】ここ数年の定番だが・・・
夏野菜の苗や種を買いに行くのは、恒例になりつつある。
でも、今年の場合、出かけたのは、半分ちょっと。
出かける、出かけないの選択ができる子どもは
なかなかすごいし、そういう保育をしているのも
なかなかすごいと思う。
保育者からすれば、一緒に行けたら・・・と思う。
でも、無理に一緒に行く必要はない。
でも、そういった仕事はしてないのに、収穫だけするとか
料理だけするとか、食べるだけとかになると、それは少し
違うかもしれない。
それまでに、どうなるかが、楽しみでもある。
そして、また冬野菜作りのときにどうなるか・・・
子どもに共通にやらせる保育は、実はそれほど難しくない。
「今から何するの?」って、
子どもが保育者に合わせてくれるから。
でも、今日みたいに選択の幅があると、保育の計画は
立ちにくくなるし、収拾がつかなくなってくる。
でも、個人として、また社会として、あなた(&わたし)はどうなの?って
子どもが向き合っていけたら、その子どもは変わっていくと思う。
そこで、ココの保育者は、未来に起こりそうなこと予測して、
何かのタイミングで、気づいたり、どうしたらいいか話し合ったり、
似たような体験も含めて、想定し、変更を加えていく。
【年少】まさか、届くとは!
ご家庭などでも、お子さんに「どうしてそんなことが!」と、
私たちの想像がつかないこと、起きますよね。
これは、そんなシーンです。
園のスタッフルーム(職員室)と廊下は、ドア1枚で区切られて、
そのドアには、カギが2つ付いています。
この日は、作業の都合でカギをかけていたのですが、
この扉を開けようと、子どもたちが何やらやっていました。
カギがかかっていると気づいていたようで、
しがばらくして静かになったので、
とうとう、あきらめたか!と思っていると・・・
イス+積み木を持ってきて、それを重ねておいて、
カギを開けたのです(ヤッタぜ!みたいな感じで)。
以前から年長児の間では、こういう姿があるのですが、
あなたたちまでも、それをするなんて。
なかなかやりおる(脱帽)!
保育者の寸劇に・・・
保育者が時々みせるちょっとした劇。そこには、
子どもたちへ、ちょっとしたメッセージも入っているのですが、
保育者の演じている姿を見る子どもの姿は実に豊か。
見入るとき・・・子どもも大人もそんなに違わないのかも。
【1歳児】遊びの流れからの検診
園庭で遊んでいるところへ、検診の先生が見えたので、
そのまま、そこで診てもらうことに・・・
(そのなんともスムーズな光景にちょっとウケました♪)
子どもたちもその流れにのせられて、穏やかなうちに
終えたのでした。
【年長】ワークショップ「はなのまま」の準備に行ったよ@前橋駅前
ここは前橋駅前。今日と明日の2日間、
「ままマルシェ」のイベントが行われるよ♪
幼稚園となかじ(中島佑太)が一緒にワークショップ
するっていうから、手伝いにきたんだ!
机をセットしたり、看板をつくったり・・・
準備が終わって、お昼ごはんを食べていたら、
前橋駅の駅長さんがやってきたよ。
駅前が、にぎわったので、なんだか、感謝されたよ。
せっかくなので、私たちも遊んだよ。
お花屋さんだと、できないことかもしれないけど、
今日は、どれを使っていいんだって。
触りほうだい、取りほうだい。嗅ぎほうだい!
絵の具と出会って、筆の代わりにしてみたり、
スタンプのようにもしてみたよ。
でも、花をこんなふうに遊びに使って・・・
それって、どうなの??と感じ人もいるかもね。
それも大切な感覚だと思うけど(感覚のマヒは困るよね!)
公園や河原のタンポポや綿毛ってどうしてる?
綿毛をとって、ふうふう飛ばしている人、けっこういるよ!
どっちも草花なのにナー。
【年少】滑り台との対話
どうして、こんなルールがあるのだろう・・・
(社会には必要なルールもありますが!)
もっと、子どもは対話する体験が必要なのに!
って思うこと、ありませんか?
例えば、公園の滑り台。
最近は使い方の看板が立っていることもあります。
これは、もし、事故が起きて(訴訟になったら・・・)
と思うと、必要な策かもしれません。
しかし、園内で滑り方を決めたらどうなるでしょう?
こういうことは起こらないかもしれませんね。
こういうことも起こらないかもしれません。
でも、ここで大切にしたいのは、「正しく遊ぶ」ことを
学ぶ(教える)のではないということ。
いろいろな滑り方を試し、経験しながら、身体と対話が起き、
周囲の子たちと対話が生まれ、滑り台を使いこなしていく・・・
正しく滑るだけであれば、それだけの滑り台ですが、何回も
繰り返し遊んでいるうちに、対話が複雑になっていきます♪
それが、「遊びの中で学ぶ」ことであって、
集団の中で一人ひとりが育っていくことです!
(滑り台も学びの宝庫ですねー)
【年長】これもアレです。
一人ひとりで作ってもいいけど、何か協力してできたらなぁ・・・
そんな私たちの願いもあって、
お家から素材(古着)をもってきてもらいました。
それを毎日、少しずつつなぐと・・・大きなこいのぼりに。
さて、どこに泳がせよう・・・?
それを探すのも、一人じゃないんです。
だって、たくさんの人が作っているから。
ちなみに、胴体はただ長いだけではありません。
古着のウロコがついていたりします!
【年中】どれもアレです。
この時期ならではのものといえば・・・?
昨日は、こうやって・・・
こんなふうにつける姿もありました。
よく、子ども一人ひとりの個性や表現を尊重しよう!とききますが、
なかなかその保育環境をつくることも難しいと思います。
でも、「〇〇は、こうあるべき」といった、枠をちょっと外すと、
どのこいのぼりも素晴らしくイイものに見えてきます♪