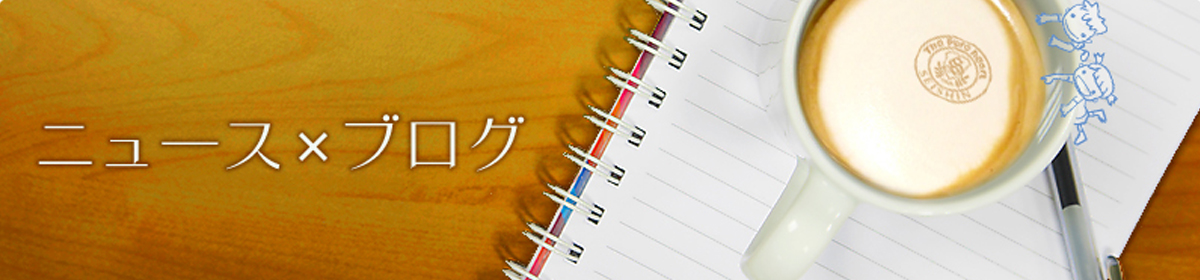天候不順な今年の9月。
雨も多いし、天気予報もあたらない。
でも、今日みたいにハズレるのはあり!
ちょうど火曜日で、お弁当を持ってきてたので、
前橋公園に行って食べたいと、どの学年も。
ついでに清心ピックをイメージして、ひろーい
場所で動いてみた。
今週の土曜日が清心ピック。
やっぱり、天気が心配。
投稿者: staff
(4歳児)たくさんの箱を使う
4歳児は、清心ピックでは、昨年と同様に箱を
いっぱい使う予定で準備をすすめています。
・・・にしても、保育室が大小さまざまな箱で
いっぱいすぎ!その数、百数十個。
当日まではまだまだ増えるとか。
これを使って、おうちの人とゲームをしたいそうです。
同じモノ(箱)でも、3歳の時はかくれんぼに使っていましたが
4歳になって、その使い方も遊び方もこんなに変わってきたんだ
そんなに育ってきてるんだ、と伝わったら嬉しいです。
ちなみに、保育室では、基地になったり、
迷路になったり、ごっこ遊びになったりしています。
何人かで使って遊びが生まれたり、積み重ねたり、
そんなところも昨年と違う姿です。
10月1日(土)は「清心ピック」へどうぞ!
<10月1日(土)は清心ピックの日>
在園児、卒業生、その家族や身内の方、
来年度入園される方、ご見学の方、
これから幼稚園を探される方、
リクルート活動や研究活動中の学生の方・・・
清心ピックは、このような方々が、参加できる
「うんどうかい」っぽいような、ぽくないような園行事です。
みなさまでお越しください!お待ちしています!!
【プログラム】 「タイトル」(対象)おおよその時間
1.「はじまりのプログラム」(一同) 8:45~
2.「はこ、はこ、はこ・・・はこ!!」(年中)
3.「おばけパーティ」(年少)
4.「Say!Shin!Map!でわっしょい!」(年長親子)
5.「ぽん!ぽんっ!ぽ~ん!」(1,2歳児親子)
6.「それゆけ!サンタロー!!」(小学生)
7.「ゆらゆらボール」(PTA幸の会)
8.「ど・れ・に・し・よ・う・か・な」(遊びにきてくれたお友だち。未就園児) 10:15~
休憩(10分)
9.おんがくげき「それそれおまつりだ!~北の大地から~」(年長feat.年中)
10.「はしって やすんで さわって!?」(年少親子)
11.「あいぼうは だるまさん」(年中)
12.「はしって パンパンパン」(祖父母)
13.「リレー」(年長)
14.「しめのプログラム」(一同)
*プログラムは受付で配布しています。
【清心ピック要項】
■日時:10月1日(土)8:45~12:00 *雨天翌日順延
■場所:前橋王山運動場
■参加できる方
①在園児・通園児
②在園・通園児の保護者
③卒園生
④在園児の祖父母
⑤来年度入園対象の方
⑥再来年度入園対象の方
⑦入園を検討されている方
⑧研究者や学生
■受付
③~⑧の方は受付で受付してください。
■駐車場
王山運動場駐車場、上越印刷様駐車場、ALSOK様駐車場
*係の指示に従ってください
■その他
*混雑が予想されますので余裕をもってお出かけください。
*各対象の競技に参加できます。
当日放送で呼びかけます。その指示に従ってください。
*ゴミは各自でお持ち帰りください。
*基本的には食事禁止です。
*禁煙です。
ザズパの応援へ
子どもたちが課外で遊んでもらっている
ザスパクサツ群馬のコーチのみなさま!
いつもありがとうございます。
本日、松本戦を応援してきました。
スタンドはかなり埋まっていたのですが、
アウェーサポーターが多くてびっくり。
少しでも勝ち点を重ねて
順位を上げて欲しいなー
(4歳児)お月見ダンゴを。
月見ダンゴを作ることになった。
なぜか、ちいさめなおダンゴになってる。
(泥ダンゴは手のひらサイズが多いけど)

今はくもり。晴れたらいいね。
(5歳児)自由な表現を振りっぽくしてみる
日中、子どもたちと遊んだり、考えたりして過ごす。
保育後、保育者が集まって、その日を振り返り、
明日を想像する。
その往還の中、「清心ピック」という、運動会風な、
でもぜんぜん違う行事もやってくる。
そんな清心ピックまであと実質2週間もない!
でも、5歳児の演目は決まってない!
演目ありきでないことは分かっていても、
焦りがないわけじゃない!
でもプロセスを大事にしたい!って思うから、
子どもに振りを与えるんじゃなく、
身体を自由に使って自由な表現で遊んできた。
(この時間が意味をもつと思ってる)
そしたら今日、ググッと何かが動き出す、
そんな瞬間が連続的に起きた。
自由な振りが、ちょっとずつ何かになっていく。
それを、子どもたちとふじちゃんが、
こうかな、あーかな、こうじゃないなとか言いながら
かためていってる。
その様子をほかの子たちも気にしながら、
一緒に見てる。
だいたいこんなかなーってなったら、
音楽をさがしてあててみる。
そして、こんなのどう?とかいくつかの曲を
流してみて選んでもらう。
そんな自由な振りから生まれてきた表現は、
音楽のイメージやテンポに縛られない。
合わさって演じても、かなりのびのびしてる。
ふじちゃんいわく、
「コンテンポラリーって感じのつくりですね」
ふじちゃんと私たち(子ども+保育者)の関係も
いい感じなんだろうなって思う。
(オトナは)焦っているけど、それを子どもに押し付けず、
いい時間を使いながら、その表現が振りになっていく・・・
「ねー、私たちのみてて!」「じゃあ、そのあと私たちね」
こどもたち同士が、見せ合ったりする姿が起きだした。
(保育者が)練習させて覚えさせる(仕込む)のではなく、
結果、自分たちで練習したくなるのは全く異なる。
こういう保育っていいなって手前みそに思う。
旅するお料理図鑑(こんわく34)
■■■■■■■■■
旅するお料理図鑑
(ゲストスペシャル)
■■■■■■■■■
■にちじ 2016年10月15日(土) 13:00~17:00
■たいしょう 図工や美術などの時間では物足りない人(小学生以上)
■もちもの ずかんをつくるのにひつようなものょ、すいとう、おやつ
■さんかひ 1,500円(材料費、保険代を含む)
■ばしょ 清心幼稚園(前橋市大手町3-1-21)
■もうしこみ FAX=027-233-0114
■メール=info@seishin-gakuen.jp(清心幼稚園)
■企画 星野怜奈(群馬大学教育学部)
===============
「こんわく」とは「今月のワークショップ」の略称です。
===============
「こんわく」は清心幼稚園で毎月行っている
子ども向けのワークショップです。
困惑しながら今月もわくわくするワークショップシリーズです。
小学生くらいから参加できます。今回が34回目!
(5歳児)ふじちゃんといろいろやってみる。
体を使って、ふじちゃんといろいろやりながら
遊んでみてる(*)。
清心ピックで子どもたちのやりたいことのひとつに
「オペレッタ」というものがある。
でも、今年はちょっと違うテイストになっていきそう。
何が生まれるかは私たちにもわからない。
どんなにもの行き着くかには不安や心配だらけ。
なるようにしかならないのだけれど。
(*)ふじちゃんとは
・「藤田善宏(ふじたよしひろ)」さんのこと
・CAT-A-TAC主宰、コンドルズメンバー
・3年ほど前から一緒に不定期に遊んでいるダンサー
・子どもたちから「ふじちゃん」とよばれている
11月12日(土)TRI4TH ライブ開催決定!
「TRI4TH ”Defying” Tour @前橋」開催!!

TRI4THが、今年も前橋清心ホールへやってきます!
圧巻の演奏とパフォーマンス。こうご期待!
■日時2016年11月12日(土)@前橋清心ホール
*OPEN17:30 START19:00
*前売り:3,000円(当日:3,500)
*別途1ドリンクオーダー
*未就学児入場不可(保護者同伴)
■ケータリング販売あります!
■託児あります!
3歳以上の未就学児をお預かりします(予めご予約ください)
■駐車場あります!
群馬県庁北駐車場がご利用いただけます
※昼の部は清心フェスティバル開催中のため今年はありません
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
予約
清心幼稚園☎027-231-2415
✉info@seishin-gakuen.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(園内研修)この地域の歴史を知る。
「幼保連携型認定こども園」の教育・保育要領には、
「地域」のことを配慮するように記されています(※)。
ここ清心幼稚園は地域とかかわる…というよりも、
地域の中で保育が必然的に行われてきました。
それは園庭が手狭なため、前橋公園をお借りしたり、
運動会では、旧前橋競輪場跡地や、利根川の河川敷
などで行ったりしなければならなかったからです。
しかし、構造的な事情だけで地域の中で保育したのでは
ありません。歴史的に、宣教師たちや地域の方、詩人
(萩原朔太郎)、画家(南城一夫)などが出入りしていて、
人的な交流も多くありました。
そこには、ヒトやモノ、そして、一人ひとりの想いの
系譜が時を超えて流れてきたように感じます。
では、これらが勝手に、自然に、受け継がれてきたか?
というと、そんなことはありません。
写真や資料等として残っている、いや、残しているからこそ
伝わっているものもあります。たとえば、今日の研修…
机に広がっている歴史資料は、10数年前、清心幼稚園の
園内研修で使用されたものだそうです。
明治期の桃井小学校の様子なども写っています。
それらを見ながら、最近の清心幼稚園の保育を語る。
資料を目にして、先輩と後輩が地域について考える。
時として、歴史の見方は変わるかもしれません。
でも、こうした記録写真や資料は、いつも変わらず、
今の私に、私たちに、問いを投げかけてくれます。
私たちは、「日常の普通」を大事に重ねたいのであって、
地域との関わりもいつのものことと思っています。
(ココの綴りも未来の歴史素材になっていくのかも!)
==========================
(※)
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」より
第3章 指導計画作成に当たって配慮すべき事項
第2 特に配慮すべき事項
(以下抜粋)
11 園児の生活は,家庭を基盤として地域社会を通じて
次第に広がりを持つものであることに留意し,家庭との
連携を十分に図るなど,幼保連携型認定こども園における
生活が家庭や地域社会と連続性を保ちつつ展開される
ようにすること。その際,地域の自然,人材,行事や
公共施設などの地域の資源を積極的に活用し,
園児が豊かな生活体験を得られるように工夫をすること。
また,家庭との連携に当たっては,保護者との情報交換の
機会を設けたり,保護者と園児との活動の機会を
設けたりなどすることを通じて,保護者の乳幼児期の教育
及び保育に関する理解が深まるよう配慮すること。
==========================