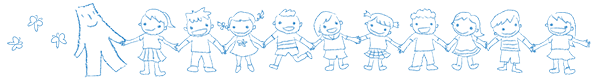これは?あれは?と、何かをしたくなる園庭や室内にしたいと考えています。「もっとこうした方がおもしろくない?」を作っていけたら理想的です。本当の遊びの面白さ、奥深さを味わうための心身をじっくり形成していきます。
*本園の「遊び」のイメージ
継続したプロジェクト的な活動、アート、身体表現、名も無い遊び(発見、いたずらなど)、フィールドワーク、栽培、感覚や知覚(聴覚・嗅覚・視覚・触覚等)など
 関わって 感じる あらわす 創発する
関わって 感じる あらわす 創発するこれは?あれは?と、何かをしたくなる園庭や室内にしたいと考えています。「もっとこうした方がおもしろくない?」を作っていけたら理想的です。本当の遊びの面白さ、奥深さを味わうための心身をじっくり形成していきます。
*本園の「遊び」のイメージ
継続したプロジェクト的な活動、アート、身体表現、名も無い遊び(発見、いたずらなど)、フィールドワーク、栽培、感覚や知覚(聴覚・嗅覚・視覚・触覚等)など

 たくさん遊んで考えます
たくさん遊んで考えます遊びの中では、身近な環境や題材と対話し、試行錯誤や工夫を通して具現化しています。周りの子どもたちや保育者と花開くケース、じっくりと熟成するケース、「ひらめく」響き合いも大切です。4歳児以降は、プロジェクト的な遊び(継続)や、ゼミ的な遊び(探究)につながります。自分が当事者(熱源)になって、子どもも大人も関係なく考えを出しあって共創しながら、そのクラスらしい生活と遊びを形成していきます。

 土と自然:育てて育つ
土と自然:育てて育つ官庁街という立地柄、広くはありませんが、野菜や果物を育てています。ウメ、サクランボ、アンズ、夏ミカン、ブルーベリーなど季節をおって生っていきます。
畑は土作りから。馴染みのある野菜から、珍しいものまでいろいろ育てます。収穫した野菜や果物は、子どもたちと加工したり、発酵させたりして「食」の豊かさを味わっています。
野菜や果物を育てながら私たちの心身もじっくりと育っていくことを大切にしています。

 ききあって、わかちあいます
ききあって、わかちあいますさまざまな人たち(現代芸術家、ダンサー、建築家、演奏者、ネイティブイングリッシュ、技術職、専門店の方など)、多様な素材や道具、出来事とかかわって対話の世界が拡がります。
自然物、人工物、時間、ファンタジー、科学、アート、光、音、色、生物などの思いや声、その世界と私とがどうなりたいのかを考え、未来の地球と生きる私たちのあり方を見つけていきます。

 ともだちと支えあって:家庭から離れて過ごす3日間(5歳児)
ともだちと支えあって:家庭から離れて過ごす3日間(5歳児)5歳児の夏、2泊3日の泊まり保育があります。お家を離れて、友だちや先生たちと過ごします。このカリキュラムは50年続く園行事の一つです。志賀高原の自然の美しさを味わって生活することはもちろん、自分のことを自分でする、子ども同士で支えあうなど、自律形成の一歩にもなっています。
夏期保育後は、友だちとのかかわりや信頼が強くなり、2学期、3学期以降の生活がより充実していきます。この時期に経験しておきたい貴重な3日間です。